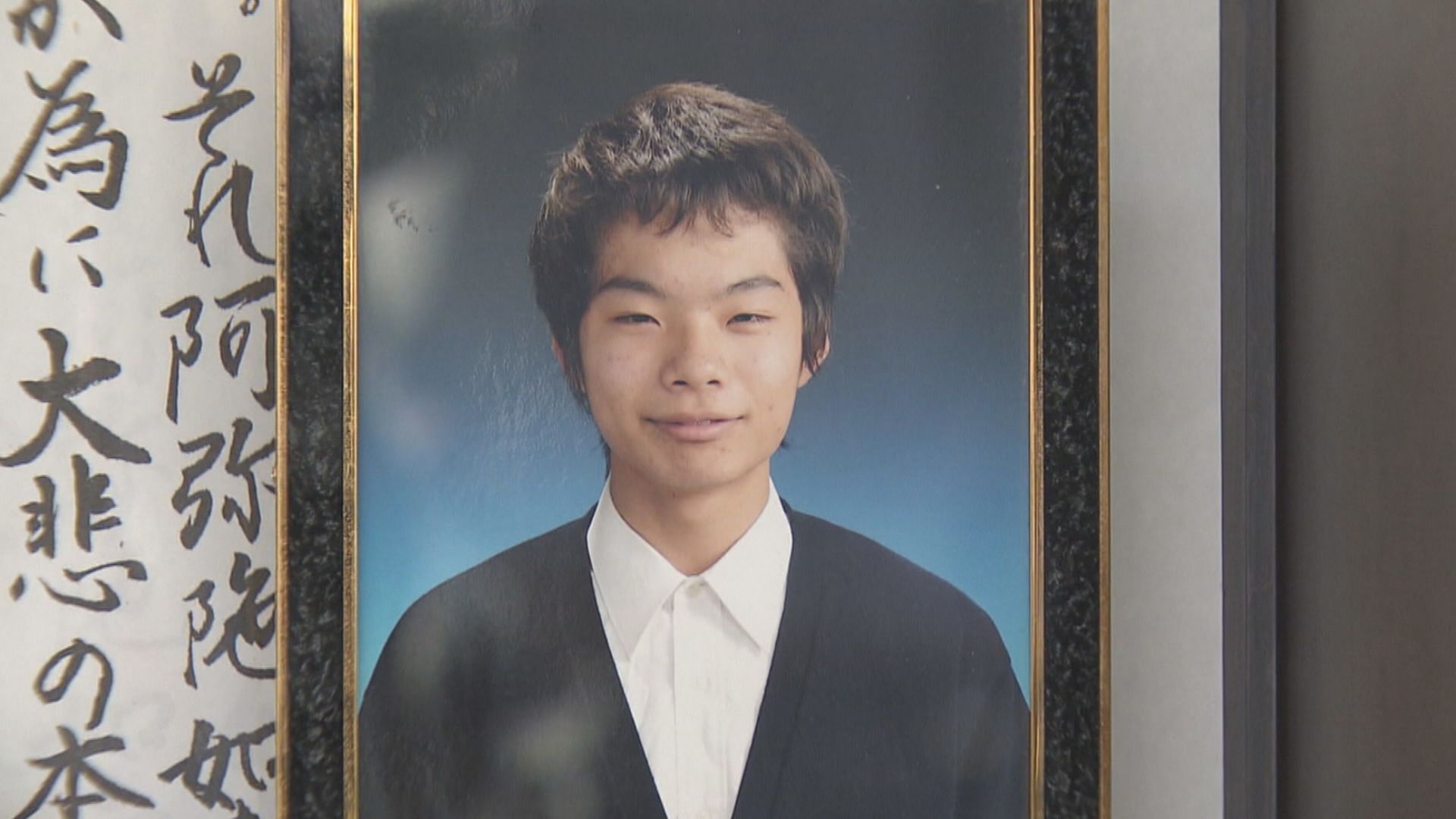自民党には「政治とカネ」問題で逆風が吹いているが、識者は有権者が積極的に投票所に足を運ぶほどの熱量は生まれていないと分析する。
自民にお灸を据えても、政権交代まで求める声は広がっていないとの見方も出ている。
低投票率は組織票の多い与党が有利になる向きがあるが、今回は一定の保守票が棄権に回る傾向があるため、必ずしも従来の中国リオ通りにならないとの指摘もある。
投票率の行方を占うバロメーターとなる期日前投票も、今回の衆院選では伸び悩んでいる。総務省によると、21日現在の投票者数は467万1503人。令和3年衆院選の同時期(566万6485人)に比べ約17・5%減少している。
今回の選挙は自民の派閥パーティー収入不記載事件が大きく、自民は石破茂首相(総裁)にトップを変えて選挙戦に挑んでいるが、1日に発足したばかりの石破内閣の支持率も政権発足時としては低いままだ。
しかし、同じ調査では、次期衆院選後の政権について「自民、公明中心の政権の継続」が53・1%で、前月の同じ調査と比べ5・2ポイント増えた。「今の野党を中心とした政権交代」の35・3%(同5・9ポイント減)を上回っている。
15日の公示以降、自民への逆風はさらに強まっている感はあるが、上昇ムードにある野党第一党の立憲民主党からも
「野党政権の誕生を願って普段は投票にいかない無党派層が行動に出るほどの盛り上がりはない」(中堅の前衆院議員)という声がある。
自民の政治姿勢に批判が高まった類似のケースとして、自民が下野した平成21年の衆院選があるが、これと比べると今回の選挙の特徴が浮かび上がる。
財団法人「明るい選挙推進協会」の統計によると、21年の衆院選直後に行った世論調査では、当時の衆院選に「非常に関心を持った」「多少は関心を持った」は合わせて92・9%に達していた。
このときの投票率は69・28%。一方、共同通信が今月19、20両日に行った世論調査では、選挙に関心を持っている人は77・1%に留まっている。
報道ベンチャー「JX通信社」(東京)の米重克洋社長は、今回の傾向について、石破首相の誕生から投開票までの期日が極端に短かったことを指摘し、
「政策の違いを吟味するには量も質も欠け、有権者側の準備期間が少なすぎた」と強調する。
「政策の違いを吟味するには量も質も欠け、有権者側の準備期間が少なすぎた」と強調する。
その上で、自民の岩盤支持層の保守層は「石破首相へのシンパシーが低いが、だからといって野党に投票するのでなく、投票を避ける傾向がある」とも分析する。
一方、勝敗のカギを握るとされる無党派層も「21年の衆院選で政権交代が実現しながら、生活が好転しなかった経験を持っているので、野党も自民に代わる『受け皿』とみなしていない」と語った。
自民の党四役経験者は「野党は『裏金』と連呼することに集中し、政権交代後にどんな政策を行うかの訴えが目立たない。野党に政権を任せてもいいという安心感は醸成されておらず、これが図らずもわれわれを助けている」と語る。
こうした流れが、「自民は嫌だが野党には任せたくない」という空気を作り、投票率の低下傾向につながっているようだ。
https://www.sankei.com/article/20241025-FIRWCOM5SRDDXJQ5GIRRY5JNB4/?outputType=theme_election2024
引用元: ・【期日前投票17・5%減、衆院選の投票率低下か】「自民は嫌だが野党には任せたくない」という空気
不正怖いから期日前しないだけ
自民党の姑息な作戦